セニョボス(Charles Seignobos 1854-1942)
『ドイツ史 ― 歴史の場面とエピソード ―』は、フランス人のためにフランス語でフランスの歴史家が書いた「ドイツの歴史」です。
著者のシャルル・セニョボスは「フランス社会がより成熟するため」に歴史学、歴史教育がどのように貢献できるかを実証主義歴史学の立場から追求しました。
さまざまな国の歴史の具体的なエピソードから社会の正確な認識をもち、現在の社会との比較を通して多様性の概念を育てる。そして社会に変化をもたらした事件や革命から、社会がどのようなことを契機として急激に、あるいはゆっくりと変化するかを知って、社会に対して無関心だったり受身でいるのではなく、変化の認識を持つことによって社会の進化をもたらすことができるようになり、急激な変化にも正しく対応できるようになる。そのために必要な批判力は、同一の歴史事実を対立する立場から見たり、異なる逸話や伝説の比較、歴史と伝説の違いなどをとおして養うことができると考えていました。
「歴史の場面」と「エピソード」で表した『ドイツ史』は、そのような背景から著したセニョボスの歴史書のひとつです。
ロシュグロス(Georges Antoine Rochegrosse 1859–1938)
挿絵を担当したミュシャ とジョルジュ・ロシュグロスは同年代です。しかし1882年にパリのサロンにデビューしてすでに名声を得ていたロシュグロスと、無名の「かけだし」だったミュシャとは全く異なる立場でした。とはいえ、共にブーランジェのもとで学び、挿絵画家のギュスターヴ・ドレを尊敬していた二人の仲はとてもよいものでした。
当初は半々の分担予定だった『ドイツ史』挿絵の8割をミュシャが描くようになっても、ロシュグロスへのミュシャの敬愛は変わらず、のちの作品、特に『スラヴ叙事詩』にはロシュグロスの影響があちこちに見られます。
ドイツの歴史
セニョボスの『ドイツ史』は、ゲルマン人がローマ帝国史に登場する西暦9年から 19世紀のゲーテとシラーまでの40の「ドイツの歴史エピソード」をとりあげています。その大半が「神聖ローマ帝国」の時代です。
ミュシャ(ムハ)は今では「チェコの画家」となっていますが、当時のチェコ(ボヘミア、モラヴィア)はハプスブルク家が支配するオーストリア帝国の領土であり、ハプスブルク家はながく神聖ローマ帝国皇帝の地位にありました。『ドイツ史』挿絵の依頼にはじめは抵抗があったミュシャですが、挿絵の場面をどう選ぶかはミュシャにまかせるというアルマン・コラン出版社の意向を得て引き受けることにしました。『ドイツ史』の場面の多くは、祖国チェコと深くかかわるエピソードだったりチェコの歴史そのものでもあったので、チェコの歴史を広く伝える機会と考えたからです。
「芸術家本来のつとめとして祖国に貢献する」というミュシャの願いは、まだ漠然としていたウィーン時代から、境遇の変遷とともにより具体的な構想へ育ちます。セニョボスの『ドイツ史』挿絵制作は、ミュシャの意識を明確にさせるとともに歴史の方法論を得ることになり、1900年パリ万博の『ボスニア・チクルス』を経て『スラヴ叙事詩』につながる仕事となりました。
『スラヴ叙事詩』が歴史のクライマックスの場面ではなく、チェコ社会に変化をもたらすきっかけとなったシーンを描いているのは、セニョボスの『ドイツ史』挿絵の経験が影響しています。『ドイツ史』の挿絵を手がける機会がなければ『スラヴ叙事詩』を描くことはなかった、少なくとも今ある形にはならなかったでしょう。
ロシュグロス
ミュシャ
ミュシャ

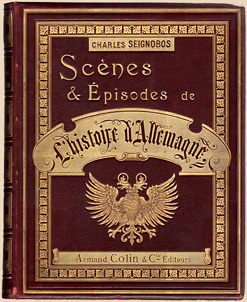
ロシュグロス
ロシュグロス
ロシュグロス
ロシュグロス
ロシュグロス
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ミュシャ
ロシュグロス