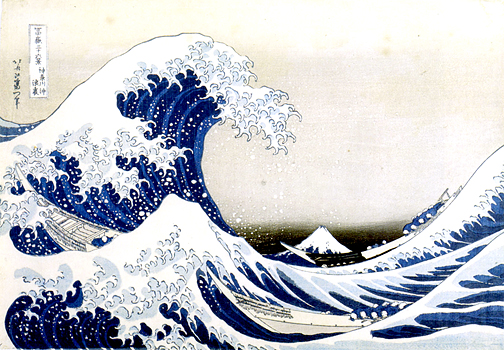右は、1898年にプラハ・トピチューヴ・サロンで開かれた、チェコ最大の美術家グループ「マーネス協会」展のポスター。
「ジャポニズムの波から若い画家たちを救え」という意味が込められている。そのようなキャンペーンが必要だったくらい、美術界のみならず欧米の社会全般で日本美術・日本文化の影響は広く深かった。
各ページの作品サムネイルをクリックしてお楽しみください。
『神奈川沖浪裏 富嶽三十六景』
(1830-1833年)
葛飾北斎 (1760-1849)
『第2回マーネス協会展』 (1898年)
アルノシュト・ホフバウアー
(Arnošt Hofbauer 1869-1944)
トップ へ